2026年1月12日
支援の方向性をそろえる!サービス担当者会議の本当の目的とは
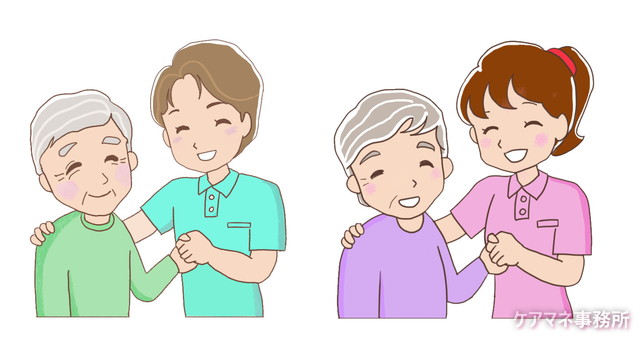
サービス担当者会議、何のためにやるの?
ケアマネとして日々業務を進める中で、
「とりあえず会議を開いておけばOK」となってしまいがちなサービス担当者会議。
でも、本来の目的を見失ってしまうと、
意味のある支援にはつながりません。
ここでは、あらためて会議の「本当の目的」を見直してみましょう📌
利用者や家族の生活と課題の共通理解🧑🦳👨👩👧
一番の目的は、「本人と家族がどんな生活をしていて、どんな困りごとを抱えているか」を
関係するサービス事業者全員で共有することです。
- 食事の用意が難しい
- 夜間に不安を感じている
- 家族の介護負担が増えている
- 生活リズムが崩れてきている
など、小さなことでも気づいておくと支援の質が大きく変わります🌱
ケアマネの声
「利用者本人が困っていないのに、事業者の常識を押しつけて“課題”を作ってしまうことも……あるかも(-_-;)」
支援側の“良かれ”が、本人の価値観とズレてしまうこともあります。
だからこそ、本人の気持ちに耳を傾ける姿勢が大切です。
地域資源やインフォーマルサービスの情報共有🏘️📬
サービス担当者会議では、制度サービスの確認だけでなく、地域の支え合い活動の情報も共有すると効果的です。
- サロンや趣味の会
- 地域包括支援センターの講座
- 地域ボランティアの配食支援
- ご近所の協力や見守り体制
こうした“地域ならではの力”をどう支援に組み込むかは、
チームの連携と工夫しだいです💡
ケアマネの工夫ポイント
- 会議の場で「最近●●の活動に参加された方いますか?」と軽く話題に出す
- 他事業者から「こんな地域情報がある」と出してもらえる場づくりをする
- 家族や本人に無理のない形で、生活に取り入れるヒントを探す
おわりに🌼
サービス担当者会議の目的は、「サービス内容を決めること」だけではありません。
本人の声にしっかり耳を傾け、地域の力も活かしながら支援の方向性を“みんなで”確認することが大切です。
本当の意味で「支える」ために。
ケアマネとして、話し合いの中身を丁寧に作っていきたいですね😊