支援がチームになる瞬間!サービス担当者会議で確認しておきたいこと
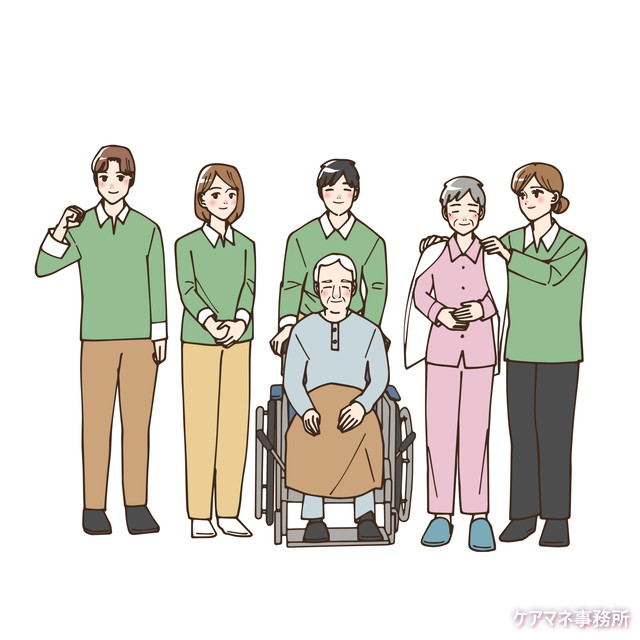
支援方針と目標をそろえることが大切
サービス担当者会議では、「どんなふうに支援していくか」「何を目指すのか」を参加者全員で確認する時間になります。
本人の生活機能をどう維持していくか、または今より少しでも良くしていくには何ができるか——
その方向性をチーム全体でそろえることが、この会議の大きな目的のひとつです📌
たとえば…
- 「一人で着替えられる時間を延ばす」
- 「昼夜逆転の生活リズムを整える」
- 「家族の介護負担を減らす」
こうした具体的な生活目標を共有することで、支援に一貫性が生まれます🌱
各サービス事業所の役割をしっかり確認🧑⚕️👩🔧
会議では、「誰がどこまでやるのか?」をはっきりさせることも大切です。
役割分担があいまいだと、支援の重複や抜けが出てしまうリスクも。
ケアマネの声
「訪問看護師やヘルパーさんで、ご自身の範囲(役割や担当)を超えてしまう方も…
ありがたいんですけど…(^^ゞ」
たとえ善意であっても、担当外の支援が続くと
「本来誰が責任を持つのか」がぼやけてしまうんです。
だからこそ、サービス担当者会議で、役割分担を明確にしておくことが基本中の基本!
「誰が、いつ、何をするか」を全員で共有しておきましょう🗂️
会議の構成メンバーも確認を
実際にサービス担当者会議に参加するメンバーは、以下のような構成になることが多いです。
- 利用者本人とその家族
- サービス事業所の担当者(訪問介護・デイ・福祉用具など)
- 主治医(参加できる場合)
- インフォーマルサービスの関係者(地域のボランティアなど)
- ケアマネジャー(計画作成者)
ケアマネの声
「地域支援者は事業者より重要なこともあります。もっと連携したいと思っていますが、実際はなかなか関わる機会が少ないです」
たしかに、インフォーマルな地域資源とのつながりは、利用者の暮らしを支える上でとても大きいものです。
でも現場では、そうした支援者を“会議に呼ぶ”ハードルが高く感じられることもあるんですよね🤔
おわりに💡
サービス担当者会議は、ただ集まって話す場ではありません。
「誰が」「何のために」「どのように支援するか」をチーム全体でそろえる場です。
特に、支援方針と役割の確認は、利用者にとって安心できる生活を実現するための土台になります😊
ケアマネとしても、会議の場づくりや関係者との調整は大変ですが、
そのひと手間が支援の質をぐっと高めてくれることを実感することが多いものです。