2025年10月10日
支援の“今”を見逃さない!モニタリングと評価でケアプランを育てる
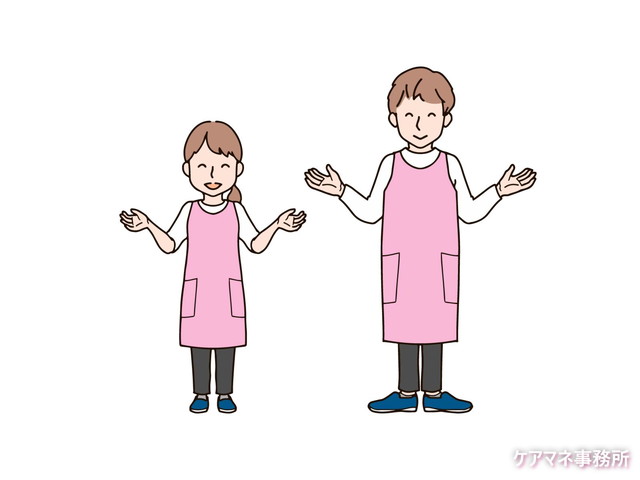
モニタリングは「支援の答え合わせ」ではない
ケアプランは作って終わりではなく、実際の生活の中でうまく機能しているかを確認していく必要があります。
そのために欠かせないのが、モニタリングと評価の視点です。
利用者の生活は毎日少しずつ変わっていきます。
だからこそ、小さな変化を見逃さず、支援を育てていくことが大切なんです🌱
モニタリングで見るべきポイント👀
モニタリングで確認したいのは、次のような点です。
- 🏠 利用者の生活状況に変化はないか
- 📋 ケアプラン通りに支援が実施されているか
- 🛠️ サービス内容が今の状態に合っているか
- 😊 利用者本人が満足しているか
- 🚧 新たな困りごとが出てきていないか
ケアマネの声
「プランに書いてないことが行われていたり、
話し相手になってしまっていたり…現実はさまざまです」
確かに、現場では想定と違うことも多いですよね。
だからこそ、確認と調整のサイクルを大事にしたいところです。
実施の方法も柔軟に📞🚗
モニタリングは「訪問だけ」と決まっているわけではありません。
以下のように、いろんな方法を組み合わせて行うのが現実的です。
サービス事業所からの報告
ヘルパーさんやデイサービスのスタッフなどから、
「最近少し元気がない」「歩行が不安定になってきた」などの声を拾います。
利用者・家族からの意見聴取
電話や訪問で直接聞き取ることも大切。
ただし…
ケアマネの声
「利用者と家族で話が違うと、どちらを信じるか悩みます…」
→ そんな時は、事業所の目や客観的なデータも参考にすると良いですよ💡
状況に応じて柔軟な対応を🔄
モニタリングの結果、「これはプランを見直したほうがいいな」と思ったら、
遠慮なく再アセスメントやサービス担当者会議を開いてOKです。
- 日常生活動作(ADL)が低下してきた
- 新たな行動障害や家族関係の変化
- 新サービス導入の必要性 など
定期訪問の「ついでにチェック」ではなく、
“必要な支援を届けるための見直し”としてモニタリングを活用しましょう✨
おわりに🧷
モニタリングと評価は、ケアマネジメントの“軸”とも言える仕事。
そしてそれは、書類や点検項目を超えて、利用者の今と未来に向き合う時間でもあります。
ケアマネとして、
「本当にこの支援でいいのかな?」と自問し続けることが、
良い支援への一番の近道になるのかもしれません😊